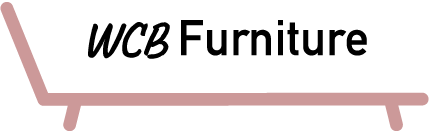日本の家具の歴史は、住まいの変化とともに歩んできました。
古代の日本では、床に直接座る生活が中心で、椅子やベッドの文化はほとんどありませんでした。その代わり、衣服や道具を収める「櫃(ひつ)」や「箪笥(たんす)」が使われ、収納家具が発達しました。
平安時代には、貴族が使う調度品として几帳や長持ちが登場し、格式を示す役割も果たします。江戸時代に入ると、庶民の暮らしにも家具が広がり、衣装箪笥や階段箪笥など、日本独自の工夫が施された家具が生まれました。
明治時代以降は、西洋文化の影響で椅子やテーブルが普及し、和の家具と洋家具が混在するようになります。そして現代では、畳の部屋と洋室の両方に合うデザインや、コンパクトな住宅に対応した収納家具が人気を集めています。
日本の家具は、住まい方や暮らしの価値観を反映しながら、時代ごとに柔軟に進化してきたのです。